日本国内で生産される鶏肉は主にブロイラー、銘柄鶏、地鶏の3種類に分かれています。
皆さんはスーパーで鶏肉を購入することがあるでしょうか。一般的に店頭に並べられているのは「ブロイラー」です。安価で手に入りやすいため、日々の食事に欠かせないお肉となっています。
今回の記事では、ブロイラーに焦点を当てて解説していきます。
ブロイラーとは
成長が早く、肉付きが良くなるように改良された商業用の種です。
短期間で出荷でき、一羽からとれる肉の量が多いため、銘柄鶏や地鶏よりも流通量は多いです。
特徴
1. 成長が早い
地鶏などの従来の鶏に比べ、肉量が増えるように改良されており、約50日前後で出荷できるほど急速に成長します。
2. やわらかい肉質
短期間で育て、筋肉が発達しきらない若鶏の状態で出荷されるため、肉は柔らかいのが特徴です。
3. 安定した供給と価格
飼育期間が短く、効率的に生産できるため、安価で安定した品質の鶏肉を消費者に届けられます。
スーパーで並ぶ鶏むね肉・もも肉の多くがブロイラーにあたります。
なぜそんなに早く成長できるのか?
ブロイラーの急速な成長には、いくつかの要素が組み合わさっています。
品種改良
ブロイラーは「肉がつきやすい体質」に改良されており、主に「ホワイトコーニッシュ」と「ホワイトプリマスロック」を掛け合わせた品種です。胸肉やもも肉が効率よく大きくなるように、長年かけて交配が繰り返されてきました。
高栄養の飼料
成長を早めるため、ブロイラーには主にトウモロコシや大豆かすを中心とした高タンパク・高エネルギーの飼料が与えられます。
地鶏が自然に近い飼料(草や穀物など)を食べるのに比べ、効率的に肉がつくように設計されています。
環境管理
温度・湿度・光の管理が徹底された鶏舎で育てられます。適温に保つことでエネルギー消費が少なく、効率よく成長します。
運動量は地鶏ほど多くないため、筋肉が硬くなりにくく、柔らかい肉質になります。
ブロイラーの歴史
ブロイラーは、自然に存在していた鶏ではなく、人間の食肉需要に合わせて生まれた「人工的な鶏」と言えます。
世界での誕生
起源は20世紀初頭のアメリカです。当時は卵を産まなくなった採卵鶏を肉用にしていましたが、人口増加や都市化の影響で「安定的に肉を供給する必要性」が高まります。
さらに戦後は、世界的にタンパク質不足が問題視されました。牛や豚よりも短期間で効率的に育つ鶏肉に注目が集まり、肉専用の鶏を開発する流れが加速します。
1940年代、ホワイトプリマスロックとホワイトコーニッシュを交配して、成長が早く肉付きのよい鶏が誕生。これがブロイラーの始まりです。
日本への導入
- 1950年代:戦後の食糧事情を改善するため、アメリカからブロイラーが導入される
- 1960年代:国内生産が広がる
- 1970年代:安価でやわらかい肉として定着し、鶏肉=ブロイラーのイメージが広まる
生産量の推移
世界的には1990年代以降急増し、現在では牛肉や豚肉を抜いて最も多く食べられる肉になっています。
生産方法
ブロイラーの生産は、効率と安定供給を目的にシステム化されています。
一貫体制(インテグレーションシステム)
ブロイラーは単一の農場ですべてを行うわけではありません。「孵化場」「養鶏農家」「食鳥処理場」「加工場」など、複数の施設が連携して生産されます。
これらを一つの大企業やグループが統合的に管理する仕組みを インテグレーションシステム と呼びます。
この仕組みにより、品質を一定に保ちつつ大量生産・安定供給が可能になります。
大規模飼育
一つの鶏舎で数千羽〜数万羽規模の鶏が育てられます。効率的な管理により短期間で大量の鶏肉が市場に供給されます。
効率的な出荷サイクル
40〜50日で出荷されるため、年間に複数回のローテーションが可能です。結果として、安価で安定した鶏肉が消費者に届きます。
生産上の問題点
効率を追求するブロイラー生産には、いくつかの課題があります。
病気や死亡率の増加
大量飼育では密度が高く、ストレスや病気のリスクが増えます。病気が発生すると、集団に広がりやすく、死亡率が高くなる場合があります。
抗生物質の使用
病気予防や成長促進のために抗生物質が使用されることがあります。過剰使用は耐性菌の問題や、人間の健康リスクへの懸念につながります。
動物福祉の課題
短期間で大量の鶏を育てるため、運動量が少なく、自然な行動が制限されます。
問題への対策
生産現場ではさまざまな対策が取られています。
- 衛生管理の徹底:鶏舎の清掃・消毒、空気や水の管理で病気の発生を最小化
- ワクチン接種:コクシジウム症や新型ウイルスなど、主要な病気に対してワクチンを使用
- 飼料の工夫:抗生物質に頼らず、プロバイオティクスやオメガ3など、健康を保つ飼料を導入
- 飼育密度の改善:適正な頭数での飼育や運動スペースの確保でストレスを軽減
こうした管理の積み重ねにより、短期間で効率的に鶏肉を生産しながらも、健康リスクを最小限に抑える努力がなされています。
まとめと豆知識
ブロイラーは、短期間で成長するように品種改良され、効率よく生産される鶏肉です。
スーパーでよく見かける鶏むね肉やもも肉のほとんどがブロイラーで、安価かつ安定供給されるのが特徴です。
しかし、大量生産ゆえに病気のリスクや抗生物質使用、運動不足による動物福祉の問題もあります。
それを防ぐため、衛生管理やワクチン、飼料の工夫、飼育密度の改善などが行われています。
豆知識
- 胸肉の量で品種改良されている
ブロイラーの胸肉は、特に大きくなるよう品種改良されており、スーパーで見る胸肉の大きさはその成果です。 - スーパーの卵はブロイラーではない
ブロイラーは成長が早すぎるため、卵を産む力は低めです。スーパーで売られている卵は、ほとんどが採卵用鶏から生まれたものです。 - 鶏の筋肉の色にも秘密がある
ブロイラーは運動量が少ないため胸肉が白っぽく、もも肉は少し赤みがかっています。地鶏のように自由に歩き回る鶏は、胸肉も赤みがかることがあります。
ご読みいただきありがとうございました。銘柄鶏、地鶏についても今後アップしていきます。
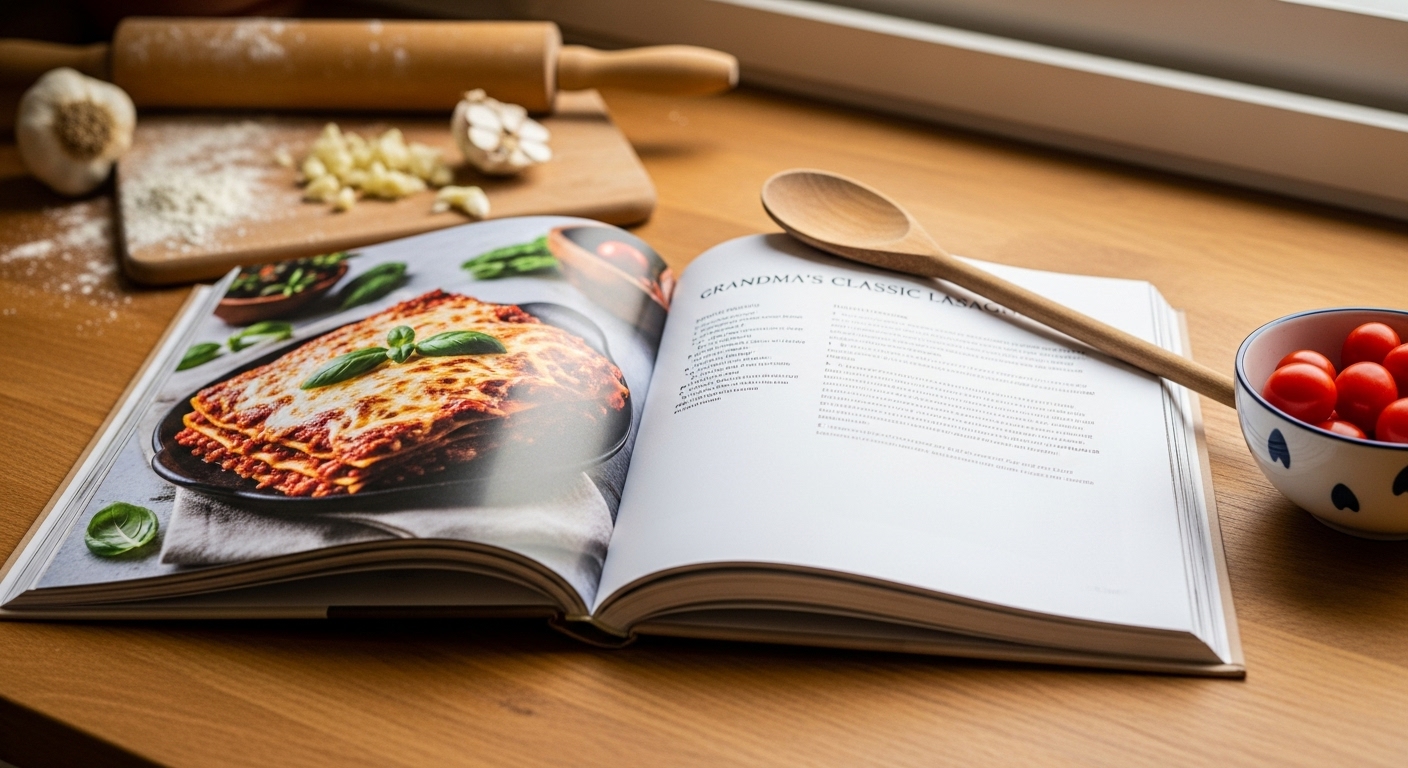


コメント